聞き覚えのある旋律が巷に流れていて、ふと誰だっけ?何という曲だっけ?という事がある。記憶を呼び覚ますのに一番のポイントはやはり旋律だが、声質というのも大きい。澄んだ高音、粘り気のある声質、しゃくりの仕方など。テレビ・ラジオ放送などからの音源の場合、曲紹介がしばらくすると流れたりして、「あぁ」となる。最近は1970年代以降最近までの曲のカバーも多く、その場合は旋律で注意を向け、「あれ」と思う。同じ曲だが声が違うのだ。もちろん編曲が違うケースも多い。カバーだから、アレンジも声も違うのは当たり前で、カバーしている歌手も原曲とその歌手の尊厳を損なわない様にしているのが感じられて不快感は無く、それはそれで良い。逆にアレンジしないと自分の声質(声域)に合わない・対応不能というケースもあるのだろう。好きな人の歌・曲を自分なりに歌う・弾くという、いわばカラオケ的なものとしてみている。上手ければ、頭の中で原曲を響かせつつシンクロさせて聴いたりできる。でも頭の中の曲の声は元のままだ。旋律だけ抽出してほぼ原形をとどめないアレンジもある。それこそ1970年代のプログレッシブロックなどに多かった。ところがそれに拠って、ポップ好きがクラシックに傾倒していくという事も発生した。悪い事では無い。元々嫌いではなかった自分は、この流れに沿ってクラシックに回帰していったクチだ。“あぁこの曲の原曲は、クラシックのあの曲なのか。”1970年代の曲を同じ流れで聴いて、“あぁ当時はこんな曲があったのか、流行っていたのか。では当時の曲を聴いてみよう…”聴き易いかたちで聴いて、原曲にたどり着くという点では「曲の浸透」がいずれかの場面で必要である。いきなり馴染みのない地球の裏側の地域の曲を聞かされても、気に入るのは数パーセント以下だろう。地域の、自国の馴染みの歌手が馴染みのない曲を歌ったら、曲は初めてでも、声が同じなら耳に届きやすいのではないか?クラシック音楽で、旋律を別としたら声にあたるモノは何だろうか。記憶に残る、自分の琴線に触れる“音”であり、それを奏でる奏者ではないのか。ただ難曲が弾ける、ミスタッチなく弾ける、では刺さらないのだ。もちろん一定以上のテクニックは必須だが、その両方を兼ね備えた者が、マエストロとして100年200年と聴き継がれてきているのだ。戦後80年で何度か電波に乗っている「上を向いて歩こう/坂本九」も、坂本九氏の声だからこそ、なのでないか。残念ながら個人的にはあまり好きではないが。
曲の浸透性
 ブログ
ブログ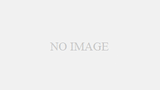
コメント