新しい楽譜を調達して練習している。練習とていると、それを聴いて曲自体を知っている人はほぼ皆無だった。「良い曲ですね」と言ってくれる人も居た。探せば、日本では知られていないけれど良い曲は沢山あるのだ。アレンジが違っているため、初めて聴いた時の曲と異なるケースもあるが、それも一興。こう弾くべし、という前例が少ない分、自分風に弾けるところも良く、世界が拡がったとすら思える。ソルを筆頭にクラシックというと一般的には限られた作曲家や作品に限定されがち(それでも大変な曲数で触れられていない曲も数多あるが)だが、年代や地域が異なっても十分鑑賞に堪える未知の曲は多い筈。作曲・発表当時は画期的で流行り、浸透していたのだろうが、その後の楽器の電気化やワールドワイドな情報の流入による多様化で、よりポップで親しみやすい楽曲が身辺にあふれて年代モノはクラシックとして一部の好事家に限られてきてしまっているのが現状。一般聴取者の取り込みと浸透を図るがために、映画音楽や現代ポップを取り入れるケースも多いが、今一つ浸透しない。ポップスにはそり/れに適した楽器があり、所詮焼き直しの感が拭えないからではないか。物珍しさからクラシックの楽器に入ってくる聴衆もいるが少ないだろう。その逆もしかり、だが、全くクラシックを知らなかったポップスファンが改めてクラシックの原曲に興味を持つケースはそれより多い。なぜならポップスも元祖はクラシックだからだ。楽典をはじめとする、曲展開・表現の仕方など、電気楽器にもある限界はクラシック楽器ではさらに狭まるのに、より表現の幅を拡げるために奏者の技量や能力が感じられ、聴衆にもそれが伝わるからという事が一点あるのではないか。もう一点は、ポップスの新楽曲が次々と生み出されるなかで、クラシックは演奏されたり発表される楽曲が凡そ限られており、奏者によって比較されるケースが多いからではないだろうか。つまり格付けされがちという事である。ポップスも浸透すると他がカバーするケースも多いが比較されるより、あのひと(奏者・歌い手)らしく、それはそれで良い、となるのが、クラシックの場合には許容範囲は狭く、“やっぱり〇〇には適わない”などの感想が出がちなのだ。不倫していようが、性格が悪かろうが、曲が良ければそれで良い、携行の強いポップスに対して、作曲者の国や時代背景・人物像・作品誕生経緯など、確かに知っていればより深く曲を理解できるかもしれないが、所詮昔の他人である。なんか勘違いしていませんか?クラシックファンの方。そのオタク発想が、自らクラシックへの一般人の敷居の高さ感を助長させているのではないですか?
流行りと浸透
 ブログ
ブログ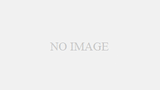
コメント