字が下手な人がいる。読めれば問題は無いのだが、数字の6・9と0、1と7など、自分はそのつもりで書いているのだろうが、他人には判読できない。漢字とひらがな、カタカナでも同様で、悪筆以前の問題ぶある。読みにくいでは無く、読めないのである。他人が読めないのはまだしも、本人ですら後で読み返して判読不能という事もある。いわゆるアタマの良いひとは、頭の回転に文字を書くスピードが追い付かないという事から悪筆が多いとされる。褒められた事では無いが、納得できるはなしである。ピカソや名だたる画家・芸術家にも当て嵌まる部分があり、作品発表時には全く世間に受け入れられず、奇人変人扱いされたと多く記述される。音楽界ではどうだろう。受け入れられなければ先ず音楽もしくは音楽家として受け入れられず、評価は0だった。一般や聴衆に受け入れられる音楽を作って初めて認められてきたのではないか。実際には音楽を含む芸術と称される世界では、一般受けせずとも、通好みの作者は多く、サロン的な世界で細々と生活してきたのではないか。そういう記述もある。彼らが悪筆だったか否かは不明だが。一般に認められても、紙一重の部分があり、各界の伝統的な考え方の頭の固い重鎮からは疎まれていたのではないか。一足飛びに才能が開花した者は、基本から一歩一歩踏み進んできた伝統を守る重鎮には理解が及ばなかったのではないか。と、想像する。なぜ理解されないのか、なぜ自分の考えが理解てできないのか。突出した者には逆に理解できなかったのではないか。その考えは超速であり、あふれ出る考え・発想を文字化するのに、そのスピードは速すぎて追い付かなかったのではないか。頭の中の曲想を表現するのに、技術が追い付かなかったのか、手足が付いていけなかったのか。そんな状況も天才の悪筆と連動する様に勝手に想像する。筆力・演奏テクニックなど最低限必要なレベルは当然だが、当時存在した技術をはるかに凌駕する曲想・画想・着想などがあったのではないか。急転直下で一般人に於いては、技術の鍛錬は遠く及ばず、自らの高まった曲想・構想・着想などを表現する技術が逆に遥かに及ばないケースが大半である。先ずは鍛錬・練習なのは当然だが、数分の演奏中のたった1か所でも、聴衆・鑑賞者に“おや”と思わせる事ができれば、万歳ではないか。レベルの差はあれど、曲や絵に対する思いは一般人でも変わらないのだから。
字下手
 ブログ
ブログ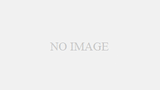
コメント