趣味でのギター。そもそも、若年層には歌の無い曲はアウトである、と認識する。歌詞が刺さるとか、言っているのを聞いても、彼らの多くは曲はメロディーラインは歌詞を補助するものであり、むしろリズムラインが重視されている様だ。インストゥルメンタルでは感情に訴えかけないのかもしれない。mfとmPの連続に因る作曲家や演奏家の訴えかけは届かない様だ。電気楽器の幅・可能性の拡がりには、到底及ばない部分も感じる。クラシックファンの年齢層の高さと、将来的なその衰退は避けられないとも感じる。一方で、クラシックファンの多くが向かうのは、オタク的な嗜好性で、“この曲は〇〇の編曲で、△△の編曲とは一味違う”など、ジャンルの素人には俄かに理解し難い。それがまたクラシックファンの自尊心をくすぐり、興味が無いやつ・わからない奴は次元が低いと標榜して、敷居をより高くしている。クラシックギターなどその最たるもので、音量・音域共に古楽器の中では群を抜いて見劣りするのだから、一層若年層の興味を削ぎ、手にする機会をも失わせている。同層の平均年齢は高齢化の一途を辿り、40歳代以下は居てもプロか余程の変わり者となっている。コンクールの数もそれなりにあるが、ジャンルとしてシニア・シルバー・マスターなどと称して、中心世代となるいわゆる老年層を対象としてきているのが歴然としている。それで良いの?大正琴と同じボケ防止の趣味レベルになっている?それでも渦中のシルバー層の大半の面々は、それなりに練習してレベルを上げて、音楽的には他の古楽器に見劣りしないのが現状である。将来性の乏しいクラシックギター界をどうしたいのか。その展望を各自持っているのか?クラシックギター及び周辺機器の商業規模は年々縮小し、重要と供給の関係から6弦セットで5、000円は下らなくなっている。週一で練習しても半年は保たない弦代や楽器の修理、まともな楽譜の大半が高価な海外製となれば、益々ファンは離れていく。ほとんど意味の無いコンクールで賞を獲っても、国民の99%以上は評価仕様もない中で、技術や音楽性を高めていき、最終的な到達点はどこに設定しているのか?複数賞を獲得したとて、それによる自身への報酬は何だと認識しているのだろうか。存在すら認識していないほとんど全ての国民を横目に、究極の自己満足で良いのだろうか。シルバー層が構成年齢の大半なら、音楽界全体やその他に働きかけるのは、残り少ない人生に只中にある者の使命とも言えるのではないだろうか。大それた事で無くとも、何かやるべく事があるのではないか?
到達点
 ブログ
ブログ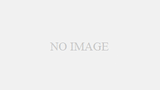
コメント