Bachの曲に多い、二声でテーマが少しずつ変わりながらひたすら最後まで続く、という構成。一か所・二か所程度の後半近くの劇的変化(それでもテーマ踏襲は変わらず)で運指が極端に困難化するが、それを克服したら終了、というパターン。でもこれが難しい。いわゆる難易度評価でも中位か下手すれば初級の上程度に位置付けられているケースもある。評価する者のレベルも、ひたすら滑らかにミスタッチなしで音符を追えていればOK的なところだろう。裏付けは無いため“だろう”としか言えないが、ノーミスタッチ・音符どおり、では曲にならない、音楽ではない、というのが論じられない日本音楽会の限界なのだ。…とは言え、というかだから猶更曲として完成させるのは難しいのだ。編曲者の技術・音楽性も大きく問われる。…でも難しい。ピアノのバイエルやギターのソル練習曲など、“練習曲なのだから、求められるとおりに弾くのが当たり前で、それが練習になる。”のは理屈だしある意味正しい。スカルラッティのK27も練習曲に準じるが、プロが弾けば十二分に聴くに堪える楽曲である。p・f・mp・mfや休符・<>などは基本的に目安であり、音を出すのはヒトである。最弱音もしくは最強音を基準にしてそれぞれ決めていくのが平均的方法で、アクセント音が大きければ次音は比較的ゆっくり続けられ、小さい・高ければ次音は間隔を置かずに続けるなど々。あくまで基準であり、そもそも運指が追い付かなければ、それらを変えねばならない。そうすると…。迷宮に迷い込まぬ様、時々誰かに聴いてもらいながら軌道修正を図るのだ。しかし基本は何度も練習を重ねる事。スポーツでも、勉強でも同じで、理論≒基本が理解できても、指や身体・設問を読み解く力などには回数が要る。平気で指をしならせて速弾できる若い人材を見ると、後は理論が追い付けば完璧だなと憧れ、同時に自分には無理だと落胆する。まぁ死ぬまでに到達できれば、か。
スカルラッティ K27
 ブログ
ブログ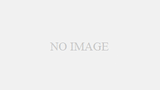
コメント